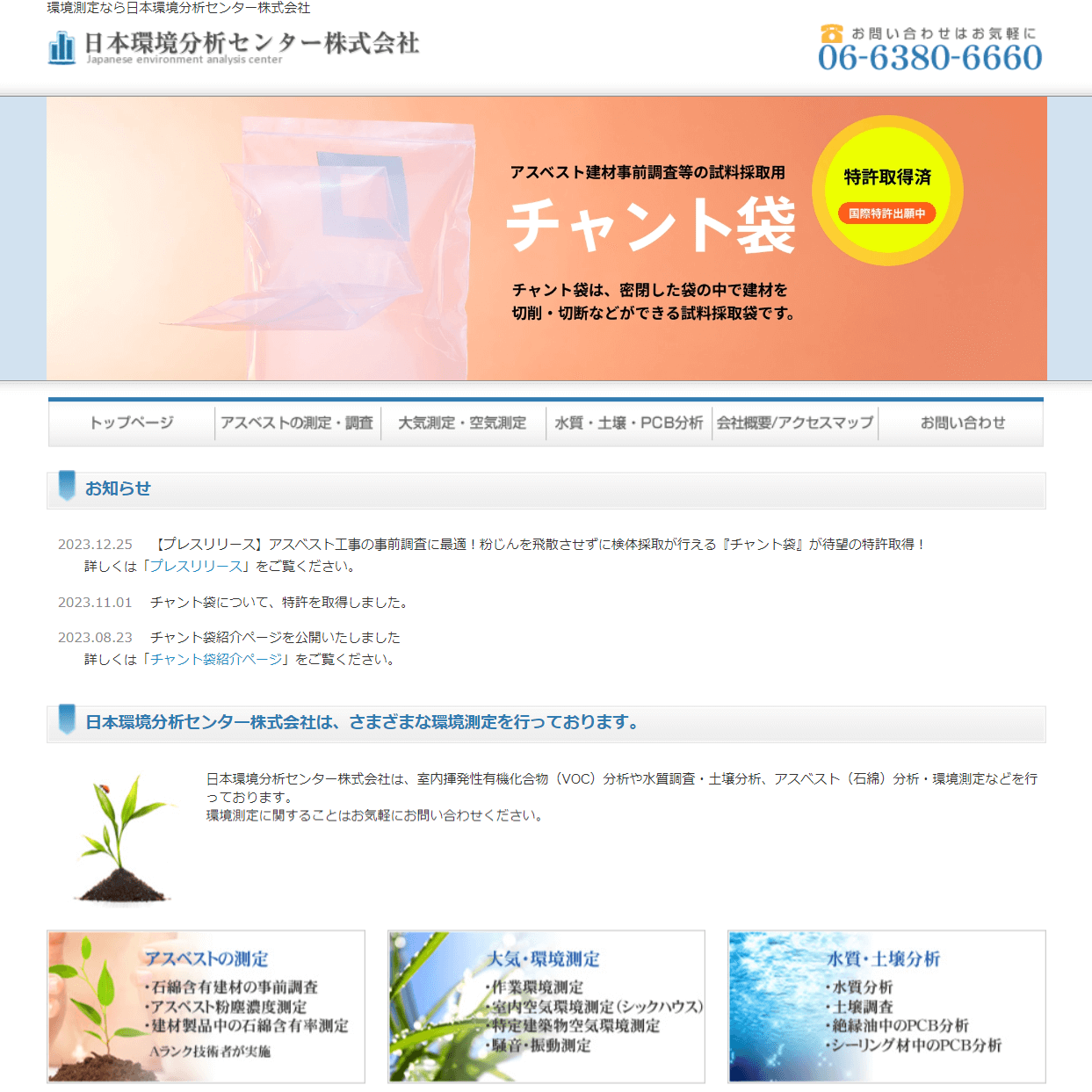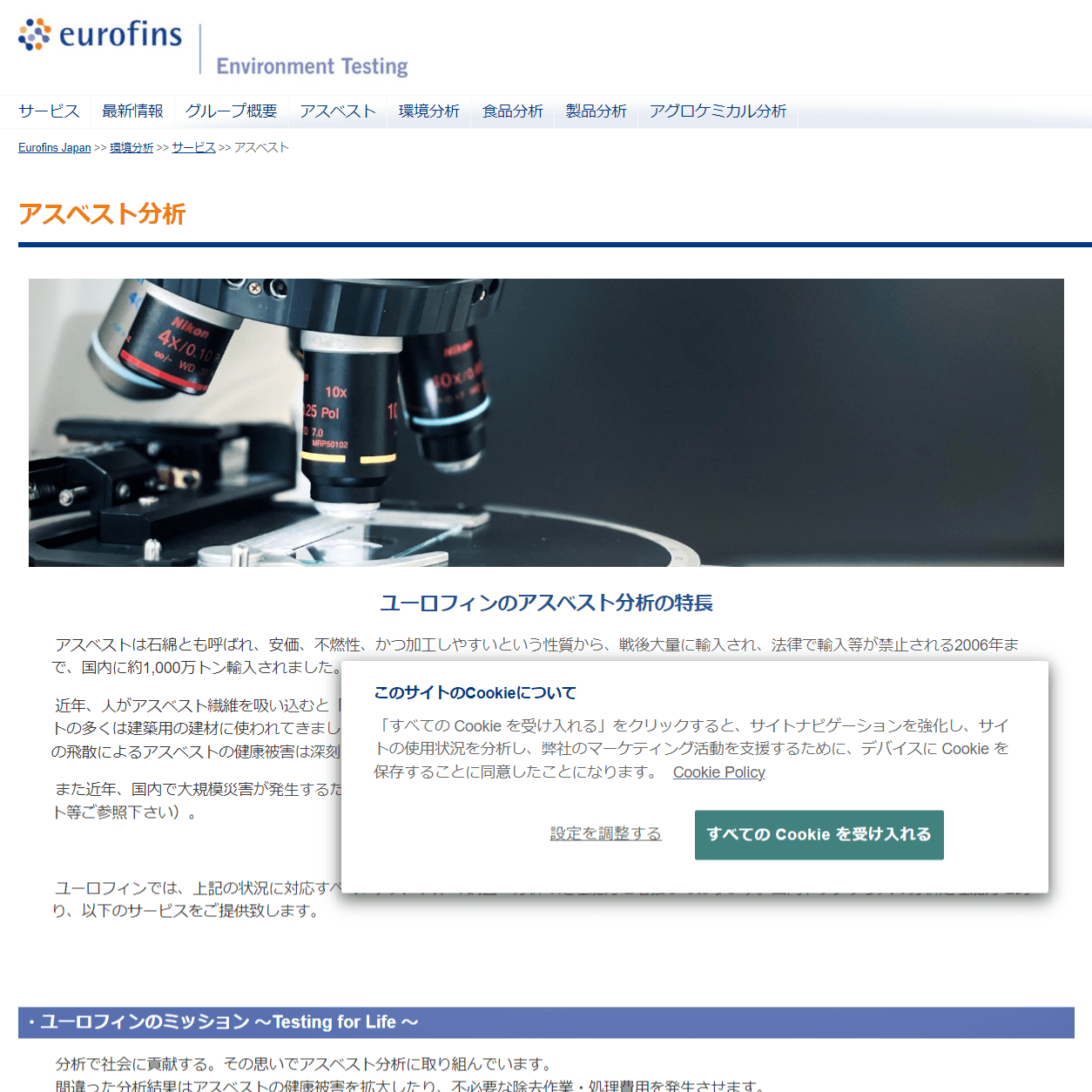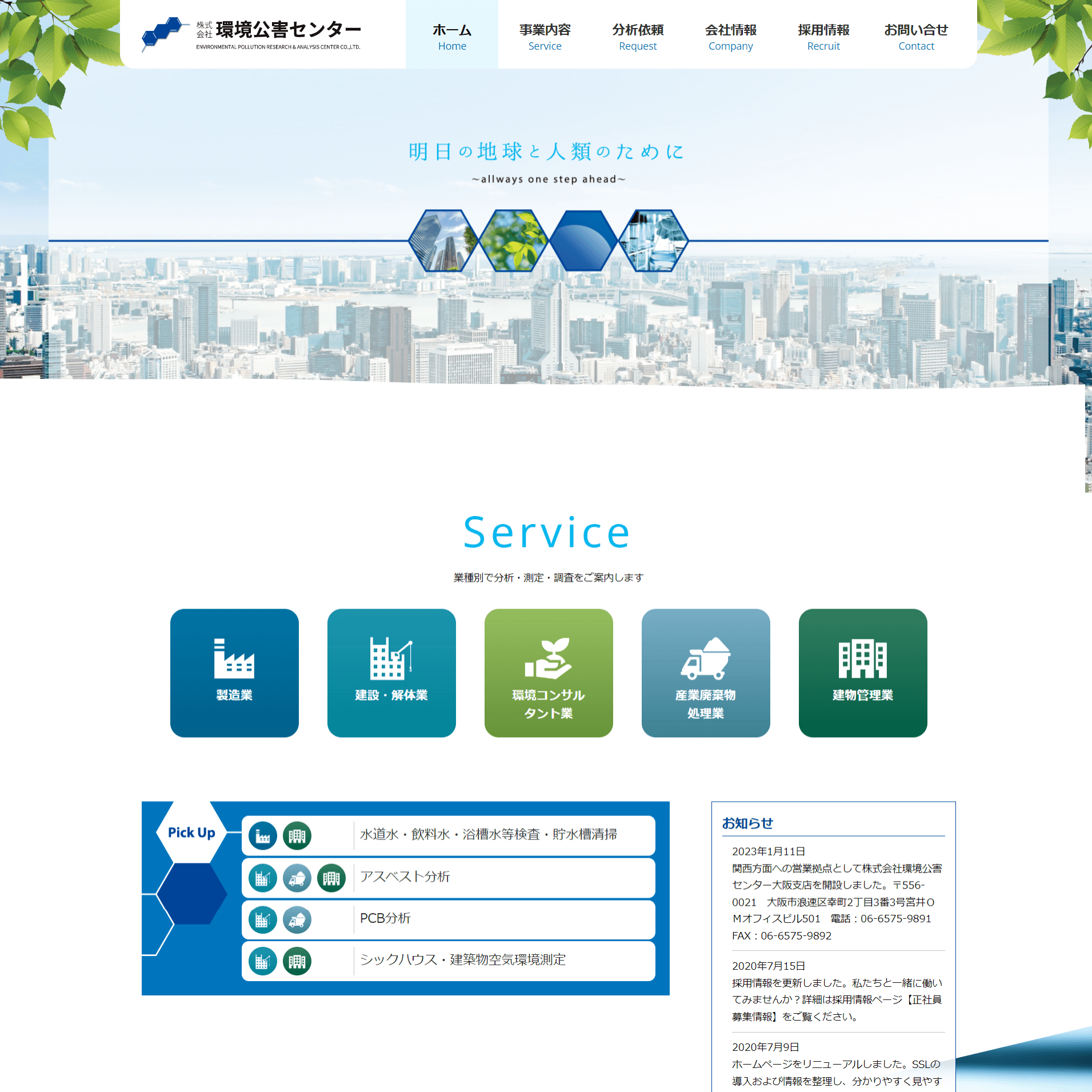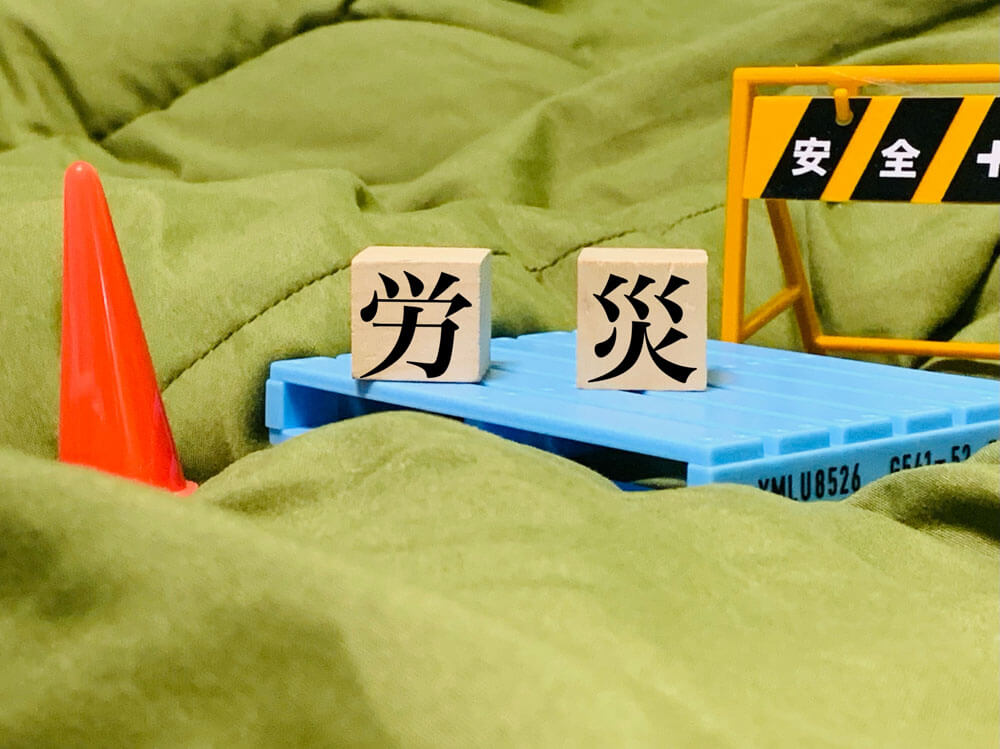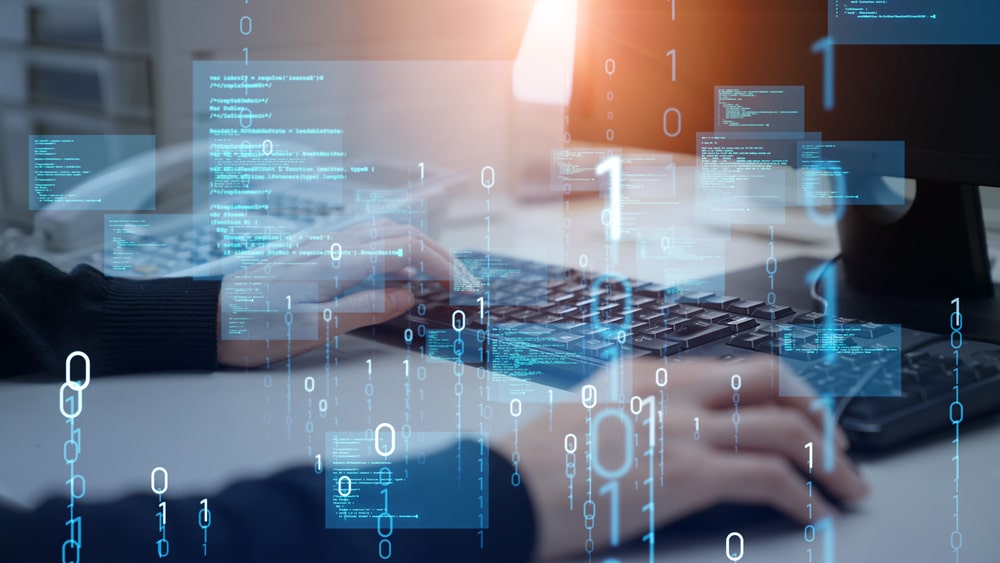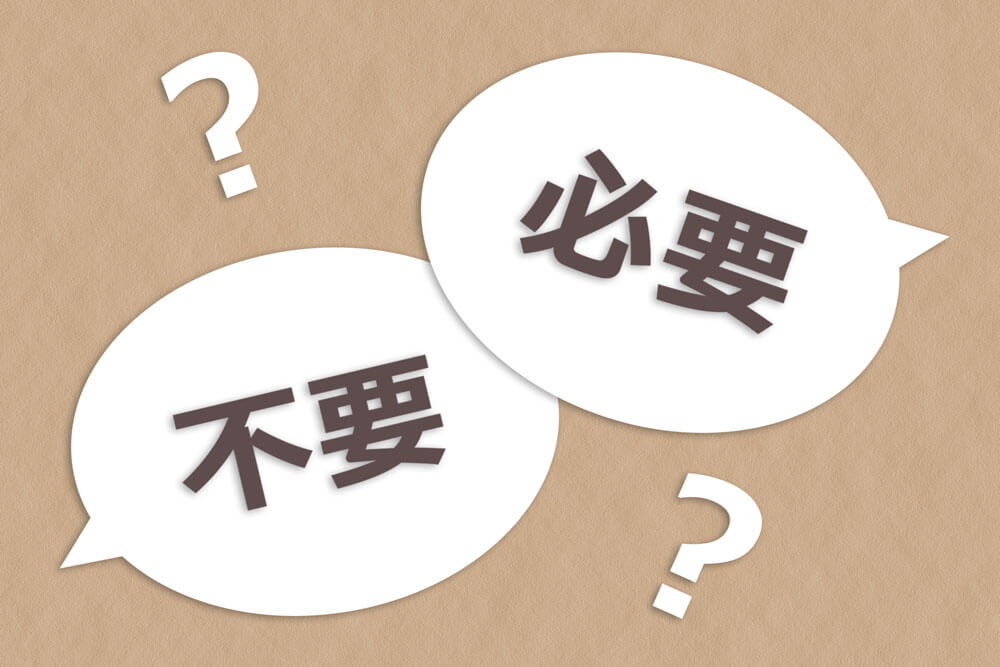建物の解体や改修工事を行う際に、アスベストの有無を確認する事前調査は法律で義務付けられています。しかし、すべての工事で調査が必要なわけではなく、素材や工法、築年によっては例外もあります。今回は、アスベスト事前調査が不要な場合と注意すべき報告義務について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
アスベスト事前調査が必要なとき
アスベスト事前調査を行うのは、おもに建築物や工作物の解体・改修工事を行うときです。理由は、アスベストが含まれている可能性がある建材を取り扱うとアスベストの粉じんが飛散し、作業者や周囲の人に健康被害を及ぼす可能性があるためです。
令和5年10月1日以降からは、有資格者によるアスベストの事前調査が義務化されています。このように、アスベストの事前調査の法規制は年々厳しくなっています。
アスベスト事前調査が不要な場合
アスベストは、人体への健康被害が深刻であることから、現在ではその取り扱いに厳しい規制が設けられています。しかし、例外的にこの事前調査が不要となるケースも存在します。ここでは、その代表的な4つのケースについて解説します。
アスベストを含まない素材を使用しているとき
まず、使用している建材がアスベストを含んでいない素材であることが明確な場合です。具体的には、木材、ガラス、石、金属などの素材で構成された建材が当てはまります。
また、畳や電球といった製品もアスベストが含まれていないことが明白であるため、調査の必要はありません。注意すべきは、これらの工事が隣接する建材に損傷を与える可能性がない場合に限るということです。
たとえば、周囲の建材を破損させてしまう可能性がある場合には、損傷があるかないかに関係なくアスベストの事前調査が必要です。
建材にほとんど損傷を与えずアスベストの飛散リスクがない場合
次に、建材を著しく損傷させることなく、かつアスベストの飛散リスクが極めて低い作業であれば事前調査はいりません。たとえば、単純な釘抜きや釘打ちなどの軽微な作業などです。
しかし、電動工具を使用する作業(穴あけ、切断、研磨など)は飛散の可能性が高まります。そのため、アスベストを含まないと思われる建材の場合にも、事前調査を行いましょう。
塗装や材料の取り付けのみを行う場合
アスベストの事前調査は、既存の建材に直接手を加える場合に必要となります。つまり、既存の建材を除去したり加工したりせず、その上に塗装を施したり壁紙を貼ったりするなど、あくまで追加作業のみを行う場合には調査はいりません。
しかし、既存の塗膜を削る、下地を研磨するといった行為は建材への損傷を伴うため、アスベストの飛散リスクが生じる可能性があります。このようなときは事前調査が必要なため、作業内容を明確に把握しておくことが重要です。
2006年9月1日以降に着工された建築物
日本では、2006年9月1日をもってアスベストの製造および使用が原則として全面禁止されました。このため、設計図書や建築確認通知書などの書面により2006年9月1日以降に新築として着工された建物であると証明できる場合に限り、現地での目視によるアスベスト調査を省略できます。
アスベストの調査が不要でも報告義務があるため注意
先述のように、アスベストの使用は2006年9月1日以降原則として禁止されています。そのため、この日以降の建築物はアスベストの含有リスクが極めて低いとされています。
しかし、これはあくまでも調査方法に関する免除であり、報告義務が全て免除されるわけではありません。実際には、一定規模以上の解体・改修工事に該当する場合はアスベストの有無に関係なく、事前調査の結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務が発生します。
一定規模以上の解体・改修工事における報告義務
報告義務が発生する代表的なケースには、おもに3つの工事が含まれます。建築物の解体工事において床面積の合計が80平方メートル以上のもの、建築物の改修工事や工作物の解体・改修工事において請負代金が税込で100万円以上のものです。
これらに該当する場合、たとえアスベストが含まれていない建材しか使用していなくても、アスベストなしという事前調査の結果を報告書として所轄の労働基準監督署に提出しなければいけません。
2006年9月1日以降に着工された建築物の場合
2006年9月1日以降に着工された建物は目視調査は不要ですが、設計図書や建築確認通知書などの着工日を証明する書面の確認が前提となります。
そのため、書面調査は必須です。さらに、一定規模以上の解体・改修工事を行う場合は、アスベストがないことの書類を所定の様式に従って労働基準監督署へ提出する必要があります。
報告に関するポイント
報告書の形式は厚生労働省が定めた「石綿事前調査結果報告書」の様式を使用します。報告のタイミングは原則として、工事開始前に提出しなければなりません。報告先は、工事現場が所在する地域を管轄する労働基準監督署です。
まとめ
今回は、アスベストの調査が不要なときと報告書について紹介しました。アスベストの調査が不要とされる場合でも、すべての工事において報告義務が免除されるわけではありません。最終的な判断は、工事内容、対象建物の性質、工事規模、関連法令に基づいて慎重に行う必要があります。不明点がある場合は、所轄の労働基準監督署や専門機関に相談しましょう。適切な手続きを行うことが、事業者としての責任を果たす第一歩となります。
-
アスベスト調査会社を決める3つのポイント
アスベスト調査の実績
対応範囲の広さ
保有資格の多さ
株式会社サン・テクノスがおすすめ!
 引用元:https://sunteqnos.co.jp/
引用元:https://sunteqnos.co.jp/- 20年を超える実績
- 事前調査から分析まで一貫して対応
- 「特定建築物石綿含有建材調査者」ほか多数の資格を保有
迷ったらここ
 アスベスト調査の実績
アスベスト調査の実績