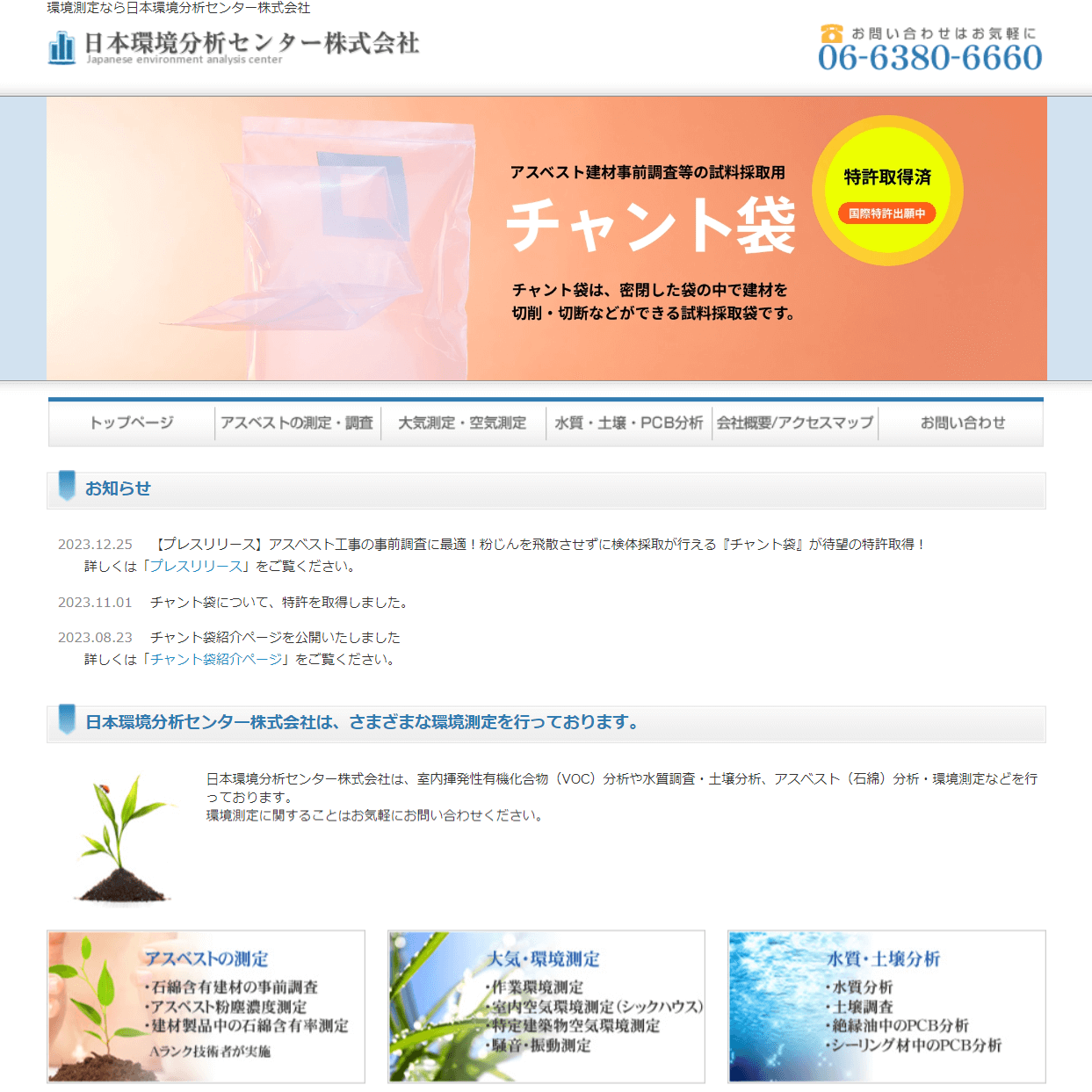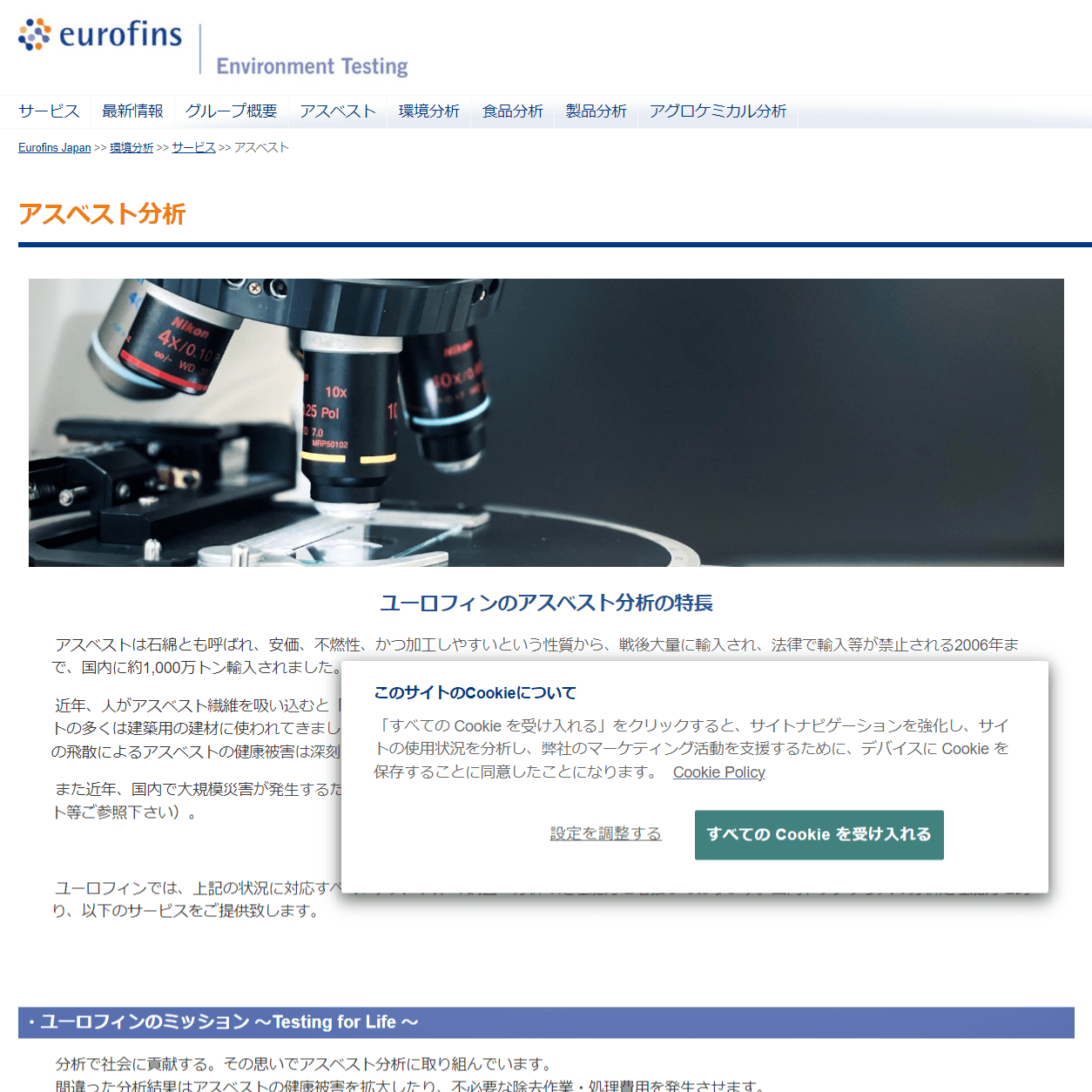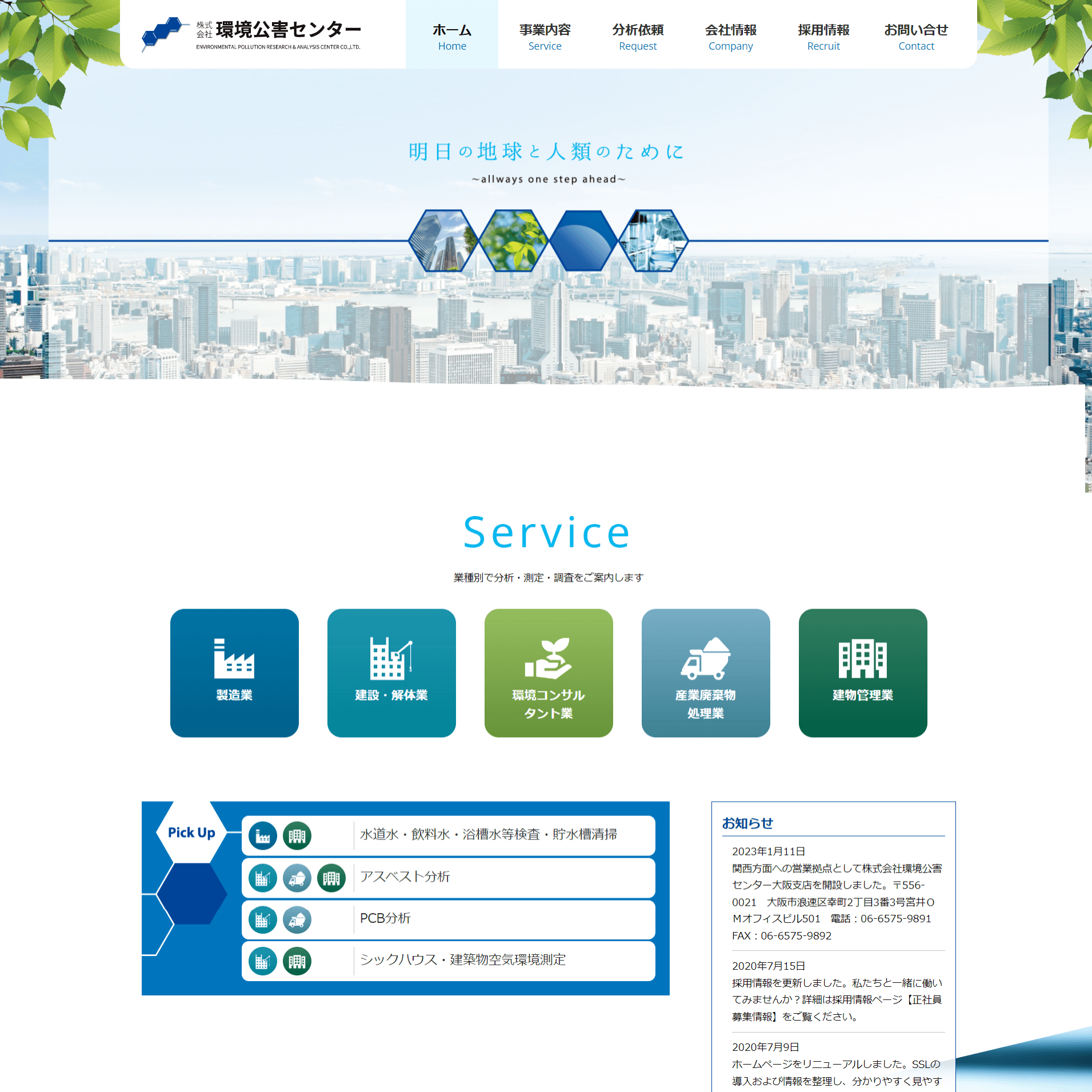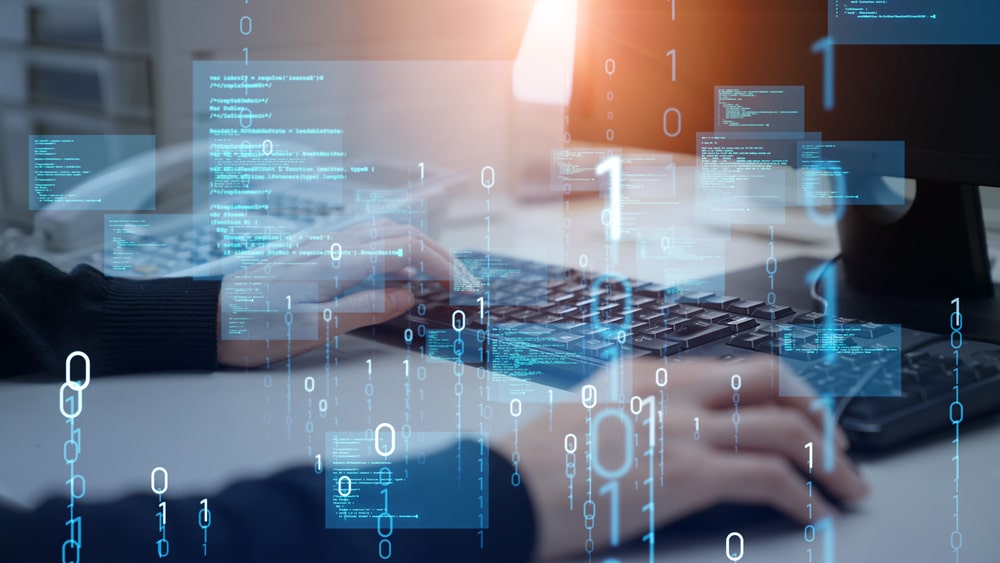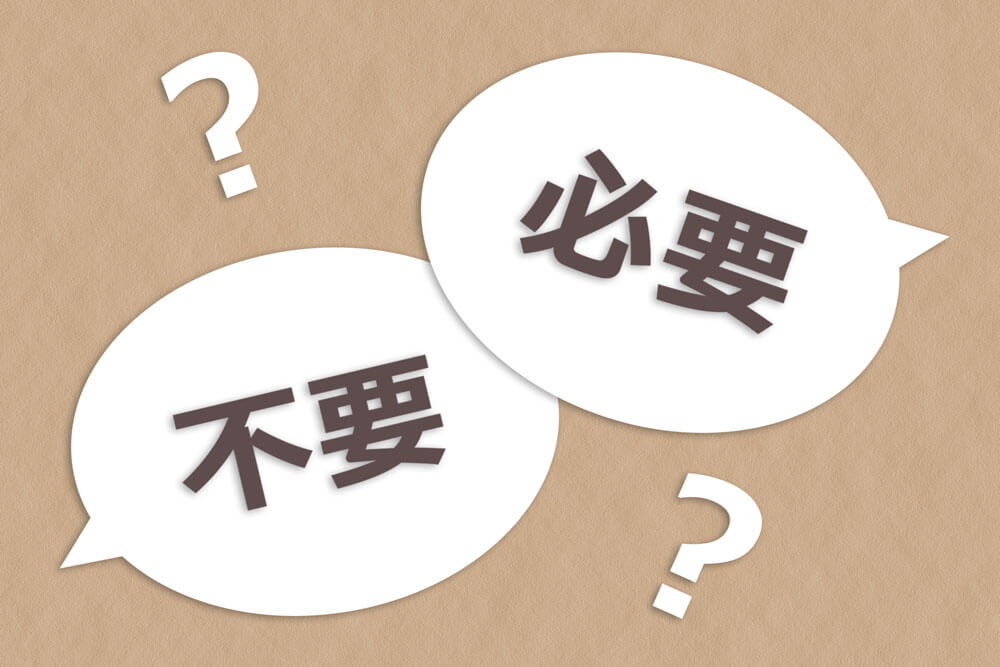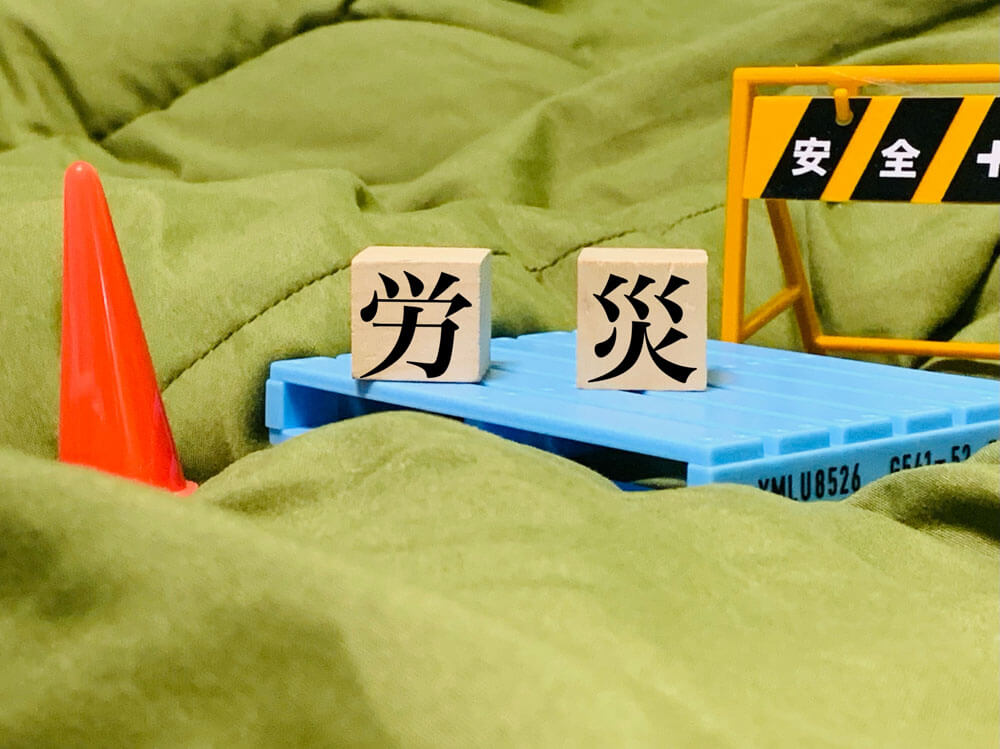アスベストは健康に被害を及ぼすことが知られると、法令が改正され段階的に規制が強化され、現在ではアスベストの製造や使用などは全面的に禁止されています。この段階的な規制の強化から、築年数でアスベストの含有が判断できるのでしょうか。そこで今回は、築年数によるアスベストの判断や、事前調査の重要性などの解説をします。
目次
築年数によるアスベストの判断はできる?
アスベストが含まれる建材が使用されている建物なのかを、築年数で断定して判断することはできません。しかし、アスベストが含まれている可能性であれば判断できます。アスベストは、高い断熱性や耐火性、耐久性があるため、多くの建物に使用されてきましたがすべての建物に含まれているわけではありません。
アスベストが含まれる可能性を判断する基準として、1975年、1995年、2006年があります。1975年に「特定化学物質等障害予防規則」が改正され、アスベストの含有率が5%を超える吹き付け作業が原則禁止されました。
そのため、規制前の1975年以前の建物はアスベストが使用されている可能性が非常に高いです。1995年には、労働安全衛生法施行令」「特定化学物質等障害予防規則」の改正により、アモサイトやクロシドライトの使用や製造などが全面禁止となり、さらにアスベストの含有率が1%を超える施工も禁止となりました。
1975年以降主流となっていた吹き付けロックウールの使用も規制されました。2006年の労働安全衛生法施行令の改正によって、アスベストの含有率が0.1%を超える製品の製造や使用などが全面的に禁止となったため、2006年以降の建物はアスベストが使用されていません。
アスベストが含まれる可能性のある箇所とそのリスク
アスベストは建物のどこに含有しているのでしょうか。ここでは、アスベストが含まれている可能性のある箇所について解説します。
屋根
住宅屋根用化粧スレートや、工場などで使用されているスレート波板にはアスベストが含まれている可能性が高いです。
外壁
外壁に使用されていた窯業系サイディングや押出成形セメント板、繊維強化セメント板にアスベストが含有している可能性があります。
内装材
内装材として使用されていたケイ酸カルシウム板やパルプセメント板にもアスベストが含まれている可能性があります。ケイ酸カルシウム板やパルプセメント板は、軽量で加工しやすいため、天井や壁などにも使用されていました。
断熱材
工場や倉庫、車庫などの屋根裏の断熱材は、アスベストが含まれている可能性が非常に高いです。また、配管やダクトに巻いている断熱材や保温材もアスベストが含有している可能性があります。
内壁の吹き付け材
内壁の吹き付け材は、アスベストが含まれている可能性が非常に高いです。1975年以前は、鉄骨造りの建物などの壁や天井裏にアスベストが吹き付けられていました。また、1975~1995年でも、吹き付けロックウールとしてアスベストが使用されていました。
-
アスベスト調査会社を決める3つのポイント
アスベスト調査の実績
対応範囲の広さ
保有資格の多さ
株式会社サン・テクノスがおすすめ!
 引用元:https://sunteqnos.co.jp/
引用元:https://sunteqnos.co.jp/- 20年を超える実績
- 事前調査から分析まで一貫して対応
- 「特定建築物石綿含有建材調査者」ほか多数の資格を保有
迷ったらここ
アスベストを放置することのリスク
アスベストは非常に細かい繊維でできているため、空気中に舞うアスベストを吸い込み体内に取り込んでしまうことがあります。体内に取り込まれたアスベストの一部は、異物として排出されますが、建材にも使用されるほど変質しにくく丈夫な物質であることから、体内にそのまま留まり、健康に影響を与えることがあるのが特徴です。
建材に使われているアスベストは樹脂などで固められているため、近くに居ても必ず危険というわけではありません。体内に入り込んでしまうきっかけと、実際にアスベストがもたらす健康被害について紹介します。
健康に影響を与えるきっかけとは?
アスベストは安価で耐熱性や摩耗性に優れていて丈夫な素材であるため、外壁や屋根といった建物の材料に用いられてきました。使用する際にセメントや樹脂といった接着剤で固めるため、建物の近くに居るだけで必ず危険ということはありません。
なんらかのきっかけでアスベストが露出することで、物質が飛散して体内に取り込んでしまいます。
リフォームや解体などの工事で建材を切断することで、粉塵に紛れてアスベストが飛散し、吸い込む危険性が高いです。材料として使用していた時期に、適切な管理のもと扱わなかったことで、知らないうちに多量に吸い込み健康に影響を及ぼす事故も発生しました。
工事に携わる業者が健康リスクを負う可能性は高いですが、建物の居住者も気を付けなければいけません。手軽に扱える高圧洗浄機で、外壁の掃除をすることで傷がつきアスベストが飛散する可能性がございます。
解体や圧力のかかる掃除などを、何もしなければ安全かというわけではありません。経年劣化によるひび割れや剥がれから、アスベスト部分が露出してしまうということもあるため、建物を放置することのリスクも十分に存在することを覚えておきましょう。
主な健康被害について
空気中のアスベストを吸い込み、肺に入れてしまうことでさまざまな病気を引き起こします。体外に排出されなかったアスベストが、肺組織内に長く滞留することで、深刻なダメージを与えることもわかっており、病気が発症するまでの期間が長いというのも特徴です。
アスベストが原因で発症しやすい病気として、中皮腫や肺がん、石綿肺などがよく挙げられます。肺や心臓など胸部の臓器を覆う膜である中皮に悪性の腫瘍ができるのが、胸膜中皮腫であり胸に水が貯まる、胸痛や息切れといった症状が多く見られます。
中皮腫は、肺がんや石綿肺と比べて低濃度のばく露でも発症する可能性があり、アスベストを扱っているような業者だけではなく、家庭内や近隣住民の発症もあり得るのが特徴です。
含まれる石綿の種類によってはより発がん性の高い物質もあり、アスベストのばく露を受けた方で喫煙をしているケースは、非喫煙者が肺がんになったときの危険性と比べて約50倍のリスクがあると報告されています。
石綿肺は長期間アスベストを吸入することで、肺が繊維化する症状のことで、現在は減少していますが、呼吸困難などを引き起こす危険な病気です。
経済的な損失
建物にアスベストが使用されていることを知りながら放置することで、経済的に損をする可能性もあります。自身が居住していて病気になり、治療費などの負担を抱えてしまうだけではなく、損害賠償や資産の価値といった面のリスクもあることを知っておきましょう。
管理責任が問われるケース
所有している物件にアスベストが使われていることを知っていた場合、適切な管理をするという責任があります。とくに所有物件を賃貸として貸し出していて、借りている人がアスベストによる健康被害を被ってしまった場合、損害賠償を求められる可能性もあり、注意が必要です。
建物を所有する際、適切な維持管理をしなければならず、建材からアスベストが飛散するような管理をしてはいけません。建物が劣化してアスベスト飛散の危険性をはらんでいる場合は、専門業者や機関に相談して貸し出す前に対処することが重要です。
実際に賃貸物件が適切な管理をされておらず、テナントとして借りていた方がアスベストの影響で、健康障害を負った事案もあり、現在ではさらに管理者が負う責任も、厳しくなっています。建物の管理を放置することで、思わぬ損害につながる危険性が存在していることは忘れてはいけません。
物件価値に関するリスク
所有物件の資産価値といった面でも、アスベストを含む建材の影響はあります。保有する物件を売却する際に、買い手も合意をしていれば、アスベストが残っていても売却は可能です。
アスベストが含まれている建物は、条件として買い手がつきにくいといったリスクもあるため、そもそも売却が難しいということもございます。双方合意のもと物件を売却できた場合でも、引き渡し後にトラブルへと発展する可能性もあるため、気を付けなければいけません。
不動産の売却時を考えたときに、建築物はアスベストの危険があり売却の不安があるため、更地にして売却をするという方法もあります。アスベストを含む建築物を解体する際には、しかるべき調査と管理のもと工事をする必要があり、問題のない建築物と比べて時間とコストの負担がかさむことが考えられるでしょう。
周囲への影響
適切な処置をせずに放置することで、自身だけではなく周囲に影響を与えてしまう可能性があることも、忘れてはいけません。意図せずアスベストを飛散させてしまい、近隣に住む方へ危険を及ぼすこともあるため、正しい知識と情報を入手することも大切です。
空き家を放置する危険性
居住していたり貸し出していたりする建物の場合は、実際に使用しているためメンテナンスなどの管理が行き届いているでしょう。近年全国的にも問題となっている空き家が、アスベストの危険をはらんでいることは、注視するべきポイントといえます。
空き家は倒壊や不法侵入などのさまざまな危険性があり、経年劣化により建材からアスベストが周辺環境に飛散していく可能性は捨てきれません。周辺地域に飛散したアスベストは、近隣住民の健康に害を及ぼすだけではなく、環境汚染にもつながりかねないため、甘く見てはいけない問題のひとつです。
意図していなくても放置することで周囲に損害を与えてしまい、責任を問われることもあります。相続した不動産で権利関係が複雑になっていて放置されていたり、建物の詳細がわからなかったりする場合は、周囲に悪影響を及ぼす前に対処しましょう。
リフォームの注意点
古い物件を自らの手で改築するDIYが人気ではありますが、正しい情報を持ったうえで工事をしているか確認する必要があります。万が一アスベスト含有の建材が使われている建物を、対策をせずに切断してしまうと自分だけではなく周囲にも被害が及ぶため、セルフで工事をしても問題ないかの確認をしなければいけません。
とくに古い物件を購入した際、建物の情報が不確かで不安を感じる場合は、アスベスト調査の専門業者に依頼して調べてもらうとよいでしょう。アスベストの含有が認められた建物は、飛散防止の措置や作業員の安全確保、廃棄物の処理方法も定められているため、専門の業者でないと工事は困難です。
手軽にリフォームができる時代ではありますが、多くの危険性や手間もあるため、アスベストの工事に関しては、詳しい知識と実績がある業者に依頼することをおすすめします。
調査時に必要な情報への影響
建物をリフォームなどで工事する際、工事業者はアスベストの調査を行う義務があります。工事業者が調査と報告を怠ることに対して罰則が設けられていますが、不動産所有者も調査の義務に関しては覚えておいた方がよいでしょう。
リフォームや解体をする際、調査費用の負担はもちろんですが、工事業者に正確な物件の情報を伝えなければいけません。今まで放置していた建物を、売却するためにリフォームや解体をしようとした際、正しい情報がわからず困る可能性がございます。
今まで問題のなかった放置物件についても、急なトラブルに見舞われるといったリスクもあるため、正しい情報を持ち早い段階で適切な対処をしておくことが大切です。
事前調査の重要性とアスベスト除去に向けた対策
アスベストの事前調査はなぜ重要なのでしょうか。ここでは事前調査とアスベスト除去に向けた対策について解説します。
アスベストの事前調査
アスベストの事前調査とは、建物の解体や改修工事前に、建物の建材にアスベストが含まれているか調査することです。アスベストは、肉眼で見ることができないほど細く、飛散すると空気中に浮遊して気付かないうちに人体に吸入される可能性が高いです。
吸入されたアスベストが肺の組織内に長く滞留することにより、肺がんや悪性中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。そのため、建物の解体や改修工事でアスベストが飛散しないように、アスベストの有無を調べる事前調査が現在は義務化されました。
アスベストの事前調査は、専門の資格を取得した調査員が調査し、発じん性の高さからレベル1~3に分類されます。
アスベストレベル1
レベル1は発じん性が著しく高いと分類されるレベルです。アスベストの除去対策は、まず工事前に事前調査結果の届出、工事計画届出、建物解体等作業届を労働基準監督署に提出します。さらに、特定粉じん排出等作業届、建設リサイクル法の事前届も都道府県庁に提出が必要です。
解体や改修工事では飛散防止のために、お知らせ看板の掲示や作業現場の徹底した清掃、作業現場の隔離や更衣室、前室の設置と届出が必要です。作業者は、防じんマスクや防護服などの着用を徹底して、厳重なばく露対策をしなければなりません。
アスベストレベル2
レベル2は発じん性が高いと分類されるレベルです。レベル2も工事前にレベル1と同様の届出の提出、さらに作業現場の隔離と更衣室や前室の設置と届出が必要です。ただし、着用する保護具に関してはレベル1より簡易的なものでも認められています。
アスベストレベル3
レベル3は発じん性が比較的低いと分類されるレベルです。レベル3は、工事計画届出、建物解体等作業届は不要です。ただし、令和3年の法令改正によりレベル3の建材も特定建築材料と認定されたため、レベル1、2と同様の義務や作業基準に従わなければなりません。
アスベストはいつまで使われていたの?
アスベストは有害物質なため現在では使われておりませんが、時期を境に有害性を危険視したために使われなくなりました。では、具体的にいつごろまで施工の際に使われていたのでしょうか。
段階的に規制がかかっていった
1975年は、特定化学物質等障害予防規則が改正され、含有率が5%をこえる吹き付けに対して規制がかかりました。1995年には、労働安全衛生法施行令と特定化学物質等障害予防規則が改正され、1%以上含まれる吹き付けが原則禁止されました。
3段階目に規制がかかったのは2004年で、労働安全衛生法施行令が改正されました。これにより、1%以上含まれる建材や接着剤などを使うのが禁止され、禁止されたものは10項目にもおよびました。
さいごの規制は2006年で、労働安全衛生法施行令が改正により、0.1%以上使われている商品をつくったり使ったりするのが禁止されました。このように、4段階にわけて規制されてきた歴史があります。
大人はもちろん、子どもや高齢者はとくに健康への被害が心配でしょう。人々が住宅や公共施設などの屋内でも健康で快適に生活や活動していけるよう、段階的にさまざま規制がなされました。
アスベストはどんな理由でどんな場所に多く使われていたか?
有害性が問題視されたためにつくられなくなったアスベストですが、なぜ広く使われていたのでしょうか。ここでは、さまざまな場所で広く使われていたわけや、どこで使われていたのかを紹介します。
高機能な建材
種類は非常に多く、3,000種類ほどあります。安くて機能的な建材なので、幅広く重宝されてきました。安価で手に入る建材は、建築費全体を安く済ませられるメリットがあるため、業者から好まれたでしょう。
また、防音性や耐火性、断熱性や絶縁性など、さまざまな機能があります。ほかにも、化学薬品にも強いという特徴があります。値段も安価で入手できたため、建築資材として幅広く用いられていました。
幅広く使われていた
安価なうえに高機能という使い勝手がよい建材ではありましたが、有害性が問題視され、現在では建材として使われていません。以前どのような場所で使われていたのでしょうか。
おもに、建材製品や工業製品として用いられてきました。ほかにも、住宅の外壁や屋根、煙突などに多く使われていました。
また、ビルなどでは、床の下地や天井で使われており、住宅のみならず公共施設などの大型な建物にも使われていたでしょう。ほかにも、吹き付け材や吸音材に入っていたため、使われていた範囲はかなり広かったといえます。
安くて機能的な建材は、さまざまな観点から求められるケースが多かったでしょう。ただ、住宅や公共施設などを使う人間に健康被害があっては本末転倒です。
人が住む住宅だけでなく、公共施設のような場所でも使われていたため、とても身近なところにあったといえます。日常的に人に影響を及ぼしていた可能性があり、つくったり使ったりするのが禁止になったのも頷けます。
屋根や外壁
屋根や外壁といった身近な場所にも使われていました。住宅用屋根の化粧スレートやスレート波板にも入っていました。スレート波板は工場などで使われているケースが多い建材です。
このようにすべての屋根に入っていたわけではなく、一部の屋根に入っていました。また、外壁といってもさまざまな種類があり、窯業系サイディングや押出成形セメント板といった外壁に入っていました。
ほかにも、繊維強化セメント板といった外壁に入っています。ただし、紹介した外壁すべてに入っていたわけではないため、含有しているか否かを判別するには、調査をすればよいでしょう。
内装材やその他の建材
屋根や外壁だけでなく、内装材にも入っていました。内装材のなかにケイ酸カルシウム板やパルプセメント板といったものがありました。これらは、アスベストが入っていた可能性のある内装材です。
軽いのが特徴的な内装材で、広く使われていました。また、加工しやすい特徴もあったため、重宝された内装材でしょう。軽くて加工しやすいため、壁だけではなく天井にも使われていました。
ほかにも、断熱材や吹き付け材にも入っていました。吹き付けロックウールという吹き付け材は、1975~1995年に使われていた建材で、多くの建築物に使われていたでしょう。
施工時期から見分けるアスベスト
施行時期によって制限されていた条件に違いがあるため、ある程度見分けがつきます。では、それぞれ具体的にどのように見分ければよいのでしょうか。
吹き付け材
さまざまな素材に入っていましたが、なかでも飛散性が高いのが吹き付け材です。吹き付け材は1971年にはつくられなくなりました。
また、1989年にはアスベストを含んだ吹き付け材がすべて製造中止になっています。つまり、1989年までアスベストを含む吹き付け材が使われていた可能性があるのです。
断熱材や耐火被覆板
断熱材や耐火被覆板は、吹き付け材に比べると飛散性は多少低いものの、比較的非酸性が高いものの分類に入ります。断熱材は家屋の断熱材や煙突の断熱材があり、それぞれつくられていた時期に違いがあります。
家屋用の断熱材は1983年までつくられていました。一方、煙突用の断熱材は1991年までつくられており、家屋用の断熱材に比べて数年長くつくられていたのです。
耐火被覆板には、ケイ酸カルシウム板と石綿耐火被覆板の2種類があります。それぞれつくられていた年月に違いがあり、前者は1965〜2004年までつくられていました。製造中止になったのは、つい20年ほど前なのです。
後者は1963〜1983年までつくられており、前者に比べるとつくられていた期間は短く感じるでしょう。また、保温材にもアスベストは入っていました。
保温材には種類が多く、バーミキュライト保温材などといった種類があります。アスベストが入っていた保温材は1920〜1987年のあいだにつくられていました。
その他建材
アスベストを含んだ建築素材は、吹き付け材や耐火被覆板のほかにもたくさんありました。ほかの建材は、吹き付け材や耐火被覆板ほど飛散性は高くありませんでしたが、有害性が問題視されていたためつくられなくなったという経緯があります。
幅広く使われていた建材のなかには、ビニル床タイルなどがあり2004年までつくられていました。また、仕上げ材はほかの建材よりも長く、2005年までつくられていました。
その他の建材は種類が多いため、製造中止時期はさまざまです。2004年の労働安全衛生法施行令の改正時点で、ほとんどの建材が製造中止となりました。
築年数のみでの判断はむずかしい
アスベストは、健康への影響により段階的につくったり使ったりするのが禁止となり、2006年の労働安全衛生法施行令の改正によりすべてが使用禁止となりました。ですから、2006年以降に建てられた建物で使われている心配はありません。
しかし、2006年以前の建物に関しては、使われている可能性があるのです。安価な点や機能面で非常に優れていたため、幅広く使われていました。
アスベストは、2006年までのあいだに段階的につくったり使ったりするのが禁止となったため、2006年よりも前に建てられた建築物に使われているか否かの判断がつきにくいといえます。実際に使われているのかを知るには、調査を依頼するとよいでしょう。
調査すれば、対象の建物で用いられていたのか、そうでないのかがわかります。調査では専門家がレベルを調べてくれるため、建築年数から自己判断せず、専門家に調査を依頼するのがおすすめです。
業者に依頼すれば、細かい部分まで調べてくれます。調査後に対策したり結果によっては安心できたりするでしょう。
まとめ
築年数によるアスベストの判断は、すべての建物に含まれているわけではないため断定はできません。しかし、アスベストが含有している可能性であれば築年数で判断できます。アスベストが含有している可能性がある箇所は、屋根、外壁、内装材、断熱材、内壁の吹き付け材などです。
また、アスベストは吸入すると健康被害を及ぼすため、建物の解体や改修工事前に事前調査することが義務付けられています。事前調査を行うと、発じん性の高さからレベル分類され、レベル1が最も飛散する可能性が高いレベルなので厳重なばく露対策が必要です。
-
アスベスト調査会社を決める3つのポイント
アスベスト調査の実績
対応範囲の広さ
保有資格の多さ
株式会社サン・テクノスがおすすめ!
 引用元:https://sunteqnos.co.jp/
引用元:https://sunteqnos.co.jp/- 20年を超える実績
- 事前調査から分析まで一貫して対応
- 「特定建築物石綿含有建材調査者」ほか多数の資格を保有
迷ったらここ
 アスベスト調査の実績
アスベスト調査の実績